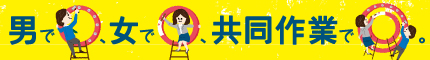このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。
ウーマノミクスを語る(2)
2018年3月号
日本政府が探る男女共同参画
|
フェニックスで話し合われた「ウーマノミクス」の会合
内閣府で発行したポスター |
|
|
日本政府が探る男女共同参画 |
日本政府では、男女共同参画を女性の側の変革のみではなく、男性にとってもプラスになる変革であるとしている。 「男女共同参画」は、男性にとっても生きがいのある社会を目指す上で重要な課題です。例えば、このような経験はありませんか。 |
男性・女性にとっての仕事と家庭のあり方について |
|
1)「男性は仕事、女性は家庭」という考え方 |
内閣府はアンケートで「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」といった考え方について、賛否を問いた。回答は、「賛成」、「どちらかといえば賛成」、「反対」、「どちらかといえば反対」、「わからない」の5つを用意し、回答者に選んでもらった。 |
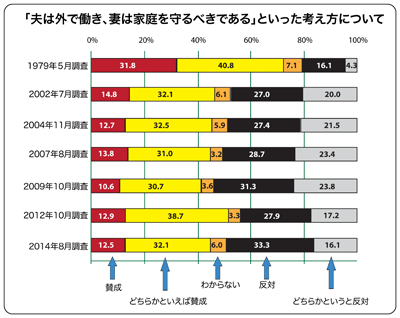 |
|
2)共働きの家庭 |
共働きの家庭は毎年増加傾向にあり、仕事の担い手と家庭の担い手に変化が生まれている。 |
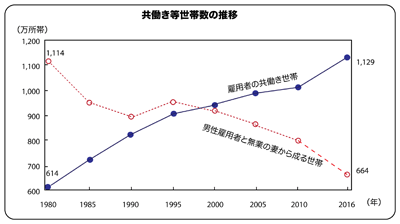 |
|
3)女性の就業継続に対する考え方 |
就業している女性に子供ができても、就業を継続する方が良いかどうか。つまり、産後も仕事を継続する女性のあり方に賛成するか、反対するか、という質問にどう回答しているだろうか。 |
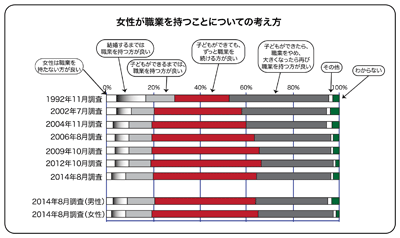 |
|
4)「稼ぐこと」に対する考え方 |
「妻にはできるだけ稼いでもらいたい」と考えている男性は、全体の2割という結果が出た。しかし、これは、男性の年齢によって、考え方が異なり、とりわけ、年齢が高くなるに従って、その数は小さくなっている。つまり、男性のジェネレーションの違いが考え方の違いとなっている。 |
男性にとっての仕事と家事・育児参画について |
|
1)男性の家事・育児参画へのイメージ |
2014年に内閣府が行った調査で、男性が家事・育児を行うことについての質問をした。その結果、男性の多くが「男性も家事・育児を行うのは当然である」と回答し、女性の多くが「子どもにいい影響を与える」と回答した。 |
2)男性の労働時間 |
週に60時間以上労働している男性就業者は、30代が最も高く、次いで40代が高くなっている。この傾向は、少しづつ減少傾向にあるが、毎年、依然、高い割合を示している。 |
3)男性の家事・育児参画時間 |
男性が家庭で、家事や育児に費やす時間は、他の諸外国と比較して、極めて低い水準を示している。 |
4)男性の育児休業取得意向と実際 |
調査によると、育児休業を取りたいと考えている男性は、3割を超えている。しかし、男性の育児休業取得率は、少しづつ上昇しているとは言え、依然として低調となっている。 |
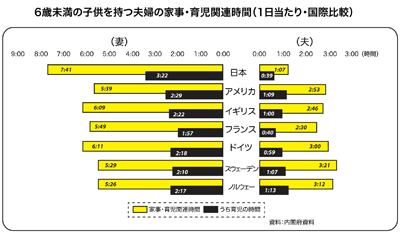 |
|
日本政府が取り組む少子化対策 |
日本政府では、現在深刻に進んでいる少子化の進行の大きな要因として、 |
子育て目的の休暇取得 |
|
1)育児休業 |
育児休業は、1歳に満たない子を養育する労働者が、事業主に対して申し出ることにより、原則として子が1歳に達する日までの連続した期間に子の養育のために取得できる休業制度である。 |
2)子の看護休暇 |
子の看護休暇は、小学校就学前の子を養育する労働者が申し出ることにより1年に5日まで病気・けがをした子の看護のために取得できる休暇である。小学校就学前の子を2人以上養育する労働者については、1年に10日まで取得できる。 |
3)配偶者の出産直後の男性の休暇取得 |
2016年の調査によると、前年2015年に父親となった男性のうち、55.9%が配偶者の出産直後の休暇を取得している。 |
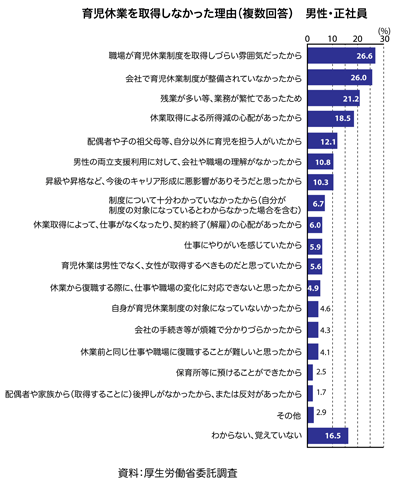 |
|
生きがいのある社会を目指して |
|
1)男性の家庭・地域参画 |
2012年の世論調査で男性が育児、子育て、介護、地域活動に参加するために必要なことは何かを質問し、その回答で最も多かったのが、「夫婦や家族のコミュニケーションをよく図ること」だった。次いで、男性自身の抵抗感をなくすこと、社会の中で家事などの評価を高めること、そして、労働時間の短縮/休暇制度の普及をすることが挙げられた |
2)悩みの対処 |
同じく2012年国勢調査で、男性の悩みの対処について質問をした。約3割の男性が「他人に弱音を吐くことがある」と回答。約6割の女性が「悩みがあったら、気軽に誰かに相談してほしい」と回答した。 |
3)自殺の原因・動機 |
2013年の自殺の状況は、内閣府と警視庁の情報からの資料が出ている。それによると、男女とも自殺の原因と動機は、「健康問題」が最も多く、男性は、「経済・生活問題」「勤務問題」が多い傾向にある。 |
4)夫婦感のコミュニケーション |
2012年の調査で、「定年後や老後の楽しみや計画の有無」と夫婦間コミュニケーションとの関係を調べた。妻とよく話す男性の多くは、「定年後や老後の楽しみや計画がある」と回答した。また、妻とあまり話さない、または、必要以外話さないと答えた男性の多くが「何もやる気がしないと感じたこと」がよく、または少しあった、と回答した。 |
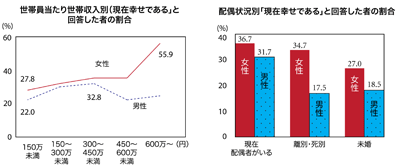 |
|
以上、日本政府が行ってきた調査結果を紹介したが、現実には、根本的な変革が長い時間をかけてスローモーションのように進んでいくのであろうか。国民の世代が変わるごとに、社会も変わらざるを得ないようになっていくことであろう。次の50年後の日本の姿を想像しながら、社会意識の変化を見つめていきたい。 |
|
内閣府で発行したポスター |
|
関連記事 |

.gif)