このページに掲載されている記事は、月刊じょうほう「オアシス」誌の記事を出版後に校正し直したものです。
インディアン・スクール、今と昔(2)
2002年6月号
先月号に引き続いて、今月もインディアン・クスールの過去を、暗い歴史の影を残しながらも、時代の変遷と同時に、インディアン・スクールも変化を遂げていく。 |
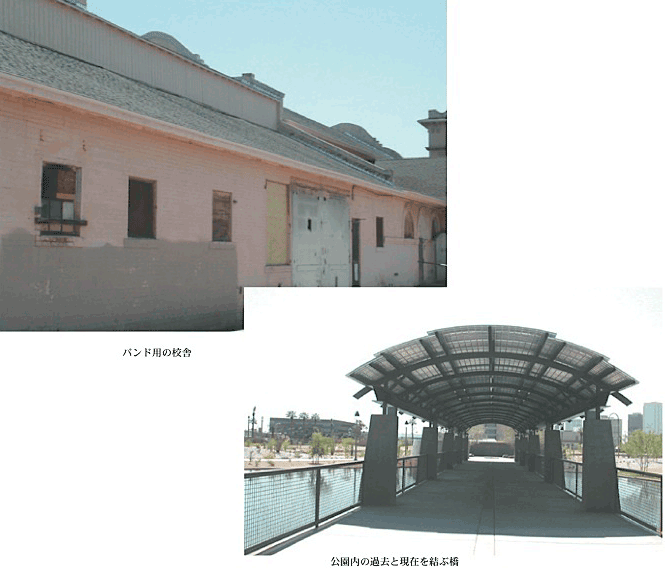 |
インディアン・スクートと音楽 |
インディアン・スクールで生徒たちが学ぶ音楽は、「文明化」されたアメリカ音楽だった。彼らは、トロンボーンやクラリネットを手に音楽の基礎を学ぶ。軍体調の教育環境のため、マーチング・バンドが組織化され、ドリル隊とバンドでパレードに参加した。 連邦政府インディアン局では、インディアンの伝統文化と伝統宗教が深く結びついていることから、キリスト教の宣教師を雇い、生徒たちがサンダンス(太陽の踊り)やゴーストダンス(幽霊の踊り)をするのを禁止し、キリスト教化と白人への同化を促進しようと懸命だった。 第一次世界大戦が始まる頃になると、生徒たちの間で新しいスタイルの音楽とダンスが流行り始めた。それは、インディアン伝統の音楽の流れを入れ込んだものだった。 これに対し、インディアン局長のチャールズ・パークは、「全インディアンに告ぐ」という文書を出した。この文書は、1923年2月23日に発行され、インディアンがインディアン局の許可なく居留区でダンスをすることを禁じ、子供たちは「より健康的な」ものを学び、より良き白人のダンスを身に付けるよう奨励したのだ。 |
蘇るインディアン文化 |
こうした政府から圧迫にも関わらず、インディアンの伝統文化が新たな息吹を見せ始めた。新しい世代の若いインディアンたちの台頭である。彼らは、インディアン・スクールで英語をマスターし、白人文化の中で生活しながら、なおかつインディアン伝統を蘇生させていくのである。 時代は変わり始めた。そして、白人社会の中でもインディアンの伝統文化や芸術に興味を示す人が増えていった。もはやこの流れを食い止めることができなくなった。観光業者もインディアンの伝統を見るコースなどを作り始めた。アメリカのフロンティアに魅せられる白人たちが増え、経済活性に寄与するようになる。 アメリカの考古学者が撮った先住民の踊りの一コマ。ニューメキシコ州のリオグランデに居住する先住民。 |
インディアン政策のアイロニー |
先住民の伝統を抹殺し、若い世代とインディアン居留区との分断を試みた連邦政府だったが、皮肉にもインディアン・スクールでの子供たちは、先祖から受け継いだ伝統のルーツをさらに強くしていき、政府を圧力を見事に乗り越えていくのである。 彼らの新しいダンスは、白人が受け入れやすくできるように、アメリカの愛国心を前面に出し、独立記念日やメモリアルデー、レーバーデーなどの祝日に、体を星条旗で包み、国家への忠誠を示しながら、見事に伝統音楽とダンスを披露していくのである。 |
連邦政府の政策転換 |
1920年代末になると、連邦政府はいよいよ自分たちのインディアン政策に誤りがあったことを認めざるを得なくなってしまった。 そして、以前から政府のインディアン政策を激しく避難してきたジョーン・コリアがインディアン局長に任命されるに至る。1933年に局長になったコリアは、大きく政策転換を図っていく。彼は、もともと、先住民の文化に魅了されていた人間で、種族の自治権を主張した。そして、インディアン・スクールでの非インディアンの音楽教育を破棄し、真のインディアン音楽を奨励するようになったのだ。彼の政策転換は大きなインパクトを社会に与え、彼の任期は1945年まで続いた。 これをインディアン・ニューディールと呼ぶ。全米のインディアン・スクールでは、インディアン・クラブができ、伝統芸術、音楽、ダンス、衣装文化を学ぶ機会が与えられた。異種部族との交流が始まり、校外でその成果を一般市民に披露するイベントも行われた。 |
インディアン・スクールとスポーツ |
さて、音楽などの分野でその特異な伝統を身につけたインディアン・スクールの生徒たちは、他の部門でも驚くべき力を示していった。 それは、スポーツである。フットボールや野球などを学んだ生徒たちは、自分が先住民の一員である誇りに燃え、白人のチームと対抗することに情熱を示した。 1890年のカーライル校のフットボールチームは、全米でも屈指の優良チームとなり注目された。それ以後、オリンピックにホピ族のルイス・テワニマ(louis tewanimaが長距離レースで銀メダルを勝ち取った。 |
関連記事インディアン・スクール、今と昔インディアン・スクール、今と昔(3) |
