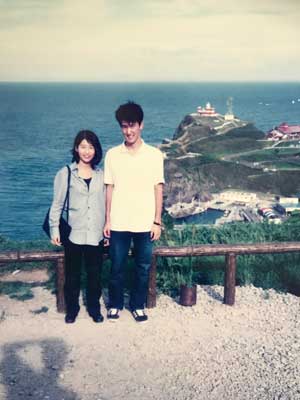心臓は、私たちの全身に血液を送り出すポンプの役を果たしている大切な器官だ。一日中休みなく働いているこの器官に少しでも支障が起これば、命に及ぶことにもなる。
日本では、「心臓」を使った言葉の言い回しが多い。例えば、厚かましい人を「心臓に毛が生えている人間」とか「心臓が強い奴」と表現し、気が弱い人は「心臓が弱い奴」と呼ぶ。また、突飛な出来事で驚くと「心臓が飛び出るほどだった」と言い、恐怖感や不安感を持つと「心臓に悪い」と表現する。また、急な傾斜を見ると、「心臓破りの坂」などと言う。臆病者を指して「蚤の心臓」などという面白い表現が使われる。
心臓は、「心」の「臓」なので、私たちの心の状態が心臓の働きに直接影響を与えていることは、昔からよく知られていた事実だ。
また、ハートの形は、愛情の表現に使われている。
夏目漱石は、彼の小説「我輩は猫である」の中で、「この時吾輩の心臓はたしかに平時よりも烈しく鼓動しておった。」と「我輩」である「猫」が持った恐れの心を表現した。
さて、私たちにとって誠に大切なこの心臓を扱う外科医として、アリゾナのツーソンで活躍している日本人がいる。
今月は、この心臓外科医の数井医師とその家族を訪ねて、お話を聞いてみた。 |
 |
数井さんの一家(自宅にて)。左から利信さん、陽仁(はるひと)君、薫さん、智尋(ちひろ)さん、沙希)沙希)さん。 |
|
|
|
アリゾナとの縁
|
数井利信さんは、現在、アリゾナ大学の大学病院で心臓外科医として働いている。その彼には、アリゾナと深い縁がある。と言うのも、彼の生まれた場所がアリゾナのフェニックスだったからだ。
彼の父は、故数井暉久氏で2015年に逝去している。故数井氏は、ドイツのハノーバー医科大学の客員教授、米国マサチューセッツ医科大学の客員教授、浜松医科大学の教授などを歴任した心臓外科医で、日本の心臓血管外科医としては、世界でもよく知られた名外科医だった。
氏は、札幌医科大学大学院医学科を修了後、1972年にアリゾナ州フェニックスのアリゾナ心臓研究所心臓血管外科にクリニカル・フェローという形で留学した。そのフェニックス滞在中に(1973年)生まれた男の子が利信さんだった。数井暉久氏は、その後、ニューヨーク州立大学医学部に移り、翌年、日本に帰国した。
利信さんは、幼少だったため、アメリカのことは全く覚えていないようだ。 |
|
|
医学を目指す
|
札幌育ちの数井さんは、札幌医科大学に入学し、父と同じ医師の道を目指す。彼に大きな影響を与えたのは、やはり父親の数井暉久氏だった。とりわけ、アメリカが心臓外科の最先端を走っている国であることを聞かされていたので、自然、アメリカへの留学を望むようになった。
彼は、札幌医科大学を卒業する時に、その先、心臓外科を目指すことを決め、日本で名医といわれている先生のもとde修行をしたいと思った。そこで、当時、国立循環器病センターの医長を経て、岩手医科大学の教授をしていた川副(かわぞえ)浩平氏のもとで修行を受けようと決めて、岩手医科大学の大学病院に入った。川副医師は、日本で弁形成術の第一人者であり、ちなみに、2012年には三笠宮崇仁親王の手術の執刀医を務めている。
|
| |
|
海外留学の夢 |
岩手医科大学で、利信さんは、助手にまでなっていた。しかし海外への留学を希望していた利信さんは、岩手医科大学の医局を離れることに決めた。そして、2008年に東京の聖路加国際病院に移ることにした。その理由は、この病院に、海外留学を希望している若い医師が多く、利信さんにとっては、最適な環境だったからである。事実、聖路加国際病院は、研修医の初期臨床研修施設としても知られており、日本の医学生にとって最も人気が高い研修先の一つとなっている。 |
|
|
ハードルが高いアメリカの医師免許取得 |
夢を追求し、諦めない。心臓外科で世界の最先端をきるアメリカで心臓外科医となりたい。その夢達成には、高いハードルを超えていかなければならない。
アメリカで医師になるためには、米国医師国家試験に合格をしなければならない。しかも英語による試験である。もともと英語が嫌いで苦手だったという利信さん。TOEFLという試験には、大変苦労したようだ。
その上に、この医師国家試験には、三つのステップがある。その試験合格後に、実際に患者を診察するという試験があり、全部で四つの段階の試験に全て合格する必要がある。その中で、ステップ1とステップ2は、日本でも受けることができるが、ステップ3と患者の診察という試験は、アメリカで受けなければならない。インターネットが発達していない頃では、アメリカの医師免許取得など、誠に不可能に近いほど難しかったとのことだ。今、インターネットの発達で、随分勉強しやすくなったが、当然、ハードルは非常に高いのが現実だ。
さて、このプロセスに挑戦を始めた利信さん。まず、聖路加国際病院にいた時に、ステップ1の合格を勝ち取ることができた。 |
| |
|
努力が呼んだ幸運の助け |
ステップ1を勝ち取った頃、願ってもない留学のチャンスがやってきた。しかも、幸運にも奨学金がおりたのである。まさに、努力と運が彼をアメリカに送ったのだ。ついに彼は、セントルイスのワシントン大学医学部に留学を果たした。
そして、2010年から2014年までの4年間、ワシントン大学に在籍した。この期間、見事、医師免許試験の全てに合格し、現場で心臓移植や心臓補助装置などの手術の経験を積むことができた。厳しい現実の壁を一つひとつ乗り越えて、努力と負けじ魂で目標達成を可能にした。 |
| |
|
アリゾナヘ |
2014年に、ワシントン大学を卒業して、その後どうするか。彼には、日本に帰るという道もあったが、もう少しアメリカで学んで上達したいという思いが強かった。彼の向上心は、さらに上を目指していた。すると、運良く、アリゾナ大学の大学病院にいる外科医から利信さんに誘いがあり、早速、彼は、アリゾナに移ることを決心する。
彼が1973年にフェニックスで生まれて再びアリゾナに戻るまで、まさに40年を超える時が経っていた。
さて、利信さんは、これまでアリゾナ大学と、一年契約で毎年更新をしていた。しかし、最近、テニュアトラック制度により、一生、アリゾナ大学で仕事を続けることが可能となった。テニュアトラック(tenure track)とは、大学が若手研究者を、任期を定めて採用し、経験を積ませた後、適格であれば終身雇用する制度だ。
つまり、利信さんの心臓外科医としての実績は、確実に大学病院で認められている、ということだ。彼は、まだ将来のことは明確になっていないが、「しばらく」の間、アリゾナにとどまって仕事をする予定だという。この「しばらく」とは、何年になるのか全く未知数である。 |
| |
|
薫さん |
この利信さんを陰で支え、3人のお子さんを育ててきたのが、妻の薫さんだ。薫さんも実は、日本で麻酔科医として働いていた。北海道の帯広で生まれた薫さんは、札幌医科大学に入学。そこで一年先輩の利信さんと会ったのが二人の交際のきっかけだった。
薫さんは、卒業後、2000年に結婚。岩手県立中央病院、札幌医科大学、岩手医科大学で麻酔科医として勤務し、2009年から聖路加国際病院麻酔科と国立がん研究センター麻酔科で非常勤として仕事をした。そして、2010年11月にご主人の利信さんと渡米をした。その時には、すでに長女の沙紀さんと次女の智尋さんが生まれており、一家4人でアメリカのセントルイスに渡った。そして、2011年には、長男の陽仁君をアメリカで出産した。 |
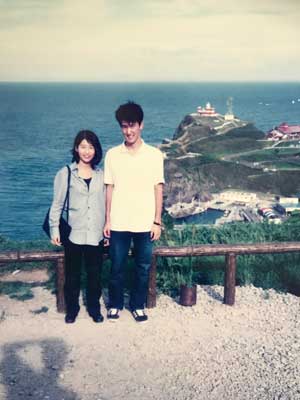
学生時代(1996年)写真提供:数井利信さん |
 |
 |
学生時代(1998年)写真提供:数井利信さん |
卒業旅行(1999年):利信さんは、右から2番目。写真提供:数井利信さん |
 |
 |
札幌医科大学水泳部(1996年):薫さんは、前列左から2番目。写真提供:数井薫さん |
学生実習(1999年)写真提供:数井薫さん |
|
薫さんの葛藤 |
アメリカに渡ったときは、利信さんのアメリカ滞在は、2年間だけの研修と思っていた。2年であれば、日本の麻酔科医として医師免許は、日本に戻った時に更新できるはずだった。そして、薫さんは、日本で再び、医師として仕事を続けることができると思っていた。
ところが、利信さんがアメリカで医師免許を取得し、アメリカ滞在は、思っていたより長引くことが明白になってきた。夫と同じように医師である自分が、夫の都合で自分の職業を諦める。彼女は、これには、かなりの抵抗感を持った。「なぜ私ばかりが夫の都合に合わせなければならないの?」との思いは、心の中に憤りと不満になり、彼女は、怒りを感じる毎日だった。
しかし、一方、ハードルの高い医師免許を取るという快挙を成し遂げた後も、アメリカ人の若い医師たちと一緒に再度、専門研究に励み、仕事のポジション探しをし、困難の壁に次々とぶつかって、どんなに難しい状況でも、諦めない夫。いつも今より向上しようと情熱を燃やし続ける夫。そんな夫のど根性を間近に見ていた薫さんは、内心、「この人はスゴイ人だ」と思うようになっていた。 |
| |
|
友人の言葉 |
セントルイス在住の時、薫さんは、ある友人にその悩みを打ち明け、相談した。そして、この友人の言葉が薫さんの心を変えることになった。それは、薫さんの葛藤の気持ちを一挙に吹っ切らせる言葉だった。
その友人は、家族というのは、一つの船のようなものだと言った。夫婦がその船をそれぞれ違う方向に漕ぎ続けたら、どこにもたどり着けない。ましてや、子供達も船に乗せているのだから、転覆してしまうかもしれない、と。まさに夫婦が人間として一緒に同じ方向に向かって船を漕いでいくのが、大切な仕事なのだと。
この友人のアドバイスで、心が吹っ切れた薫さんは、家族を守ることを我が使命と捉えていけるようになった。今は、毎週土曜日に智尋さん(中学1年)と陽仁君(小学2年)を連れて、メサにある日本人補習校のアリゾナ学園まで、ツーソンから2時間ほど運転して送り、授業が終わると再び2時間かけて運転して自宅に戻ってくるという生活をしている。また、平日の月曜から金曜は、3人の子供を現地校に送り、かつての麻酔科医は、家庭と夫を支える仕事に余念がない。 |
| |
|
アメリカの医療 |
アメリカで医師として仕事をする利信さん。世界の医療技術の最先端を走るアメリカで医師免許を取得した彼が悲しく感じるのは、この国の医療システムだという。
患者が来院してきても、保険がなく治療を受けられない人を多く見ている。保険料が高い「良い」保険を持っていれば、手術を受けることができるが、「良い」保険を持ってない患者は、個人負担で手術を受けることになる。時には、手術をしなければ、死んでしまうという患者に、手術ができないことがある。
また、ツーソンには、不法滞在者が多い。メキシコなどから不法でアメリカ国内に入り、何十年もツーソンに住んでいる人が病気になる。しかし、不法滞在者には、医療の手は届かない。
しかも、保険会社が医師を牛耳るということもある。
アメリカは、こうした大きな矛盾を抱えるこの国だが、医師として人の命とか関わる利信さん、そしてご家族の今後の活躍に期待したい。 |
| |
|
数井利信心臓外科医に聞く
「心臓病にならないために気をつけること」 |
以下が数井医師の回答。
心臓病は治療より予防が簡単です。
1.アメリカに住んでいると、日本と違い、健康診断等を職場でしてくれることは、少ないと思います。自分でプライマリーケアにかかり、健康状況を確認することが必要になります。
2.また、車社会なので、普段歩いて移動することが少なくなるため、普段の生活に、意識的に運動を取り入れることが必要になります。
3.アメリカの食事は塩分、糖分、脂質が多く含まれています。また、清涼飲料水、炭酸飲料もどこでも大変安く手に入るので、これらを過剰摂取すると、高血圧、糖尿病、高脂血症を発症してしまいます。このような基礎疾患が冠動脈疾患、動脈瘤などの危険因子になります。一度これらの基礎疾患を発症しても治療をしてコントロールすることでリスクを下げることができます。
4.歯周病等の口腔内感染も、心臓弁膜症を起こすリスクファクターなので、定期的に歯科でクリーニングを受けることが大事だと思います。
最後に、特にアメリカでは健康管理も自己責任となってしますので、面倒ですが、プライマリーケアドクターにかかり、歯科でクリーニングを受けるというような管理が大事だと思います。
症状がひどくなる前に病院にかかってください。 |
| |
|