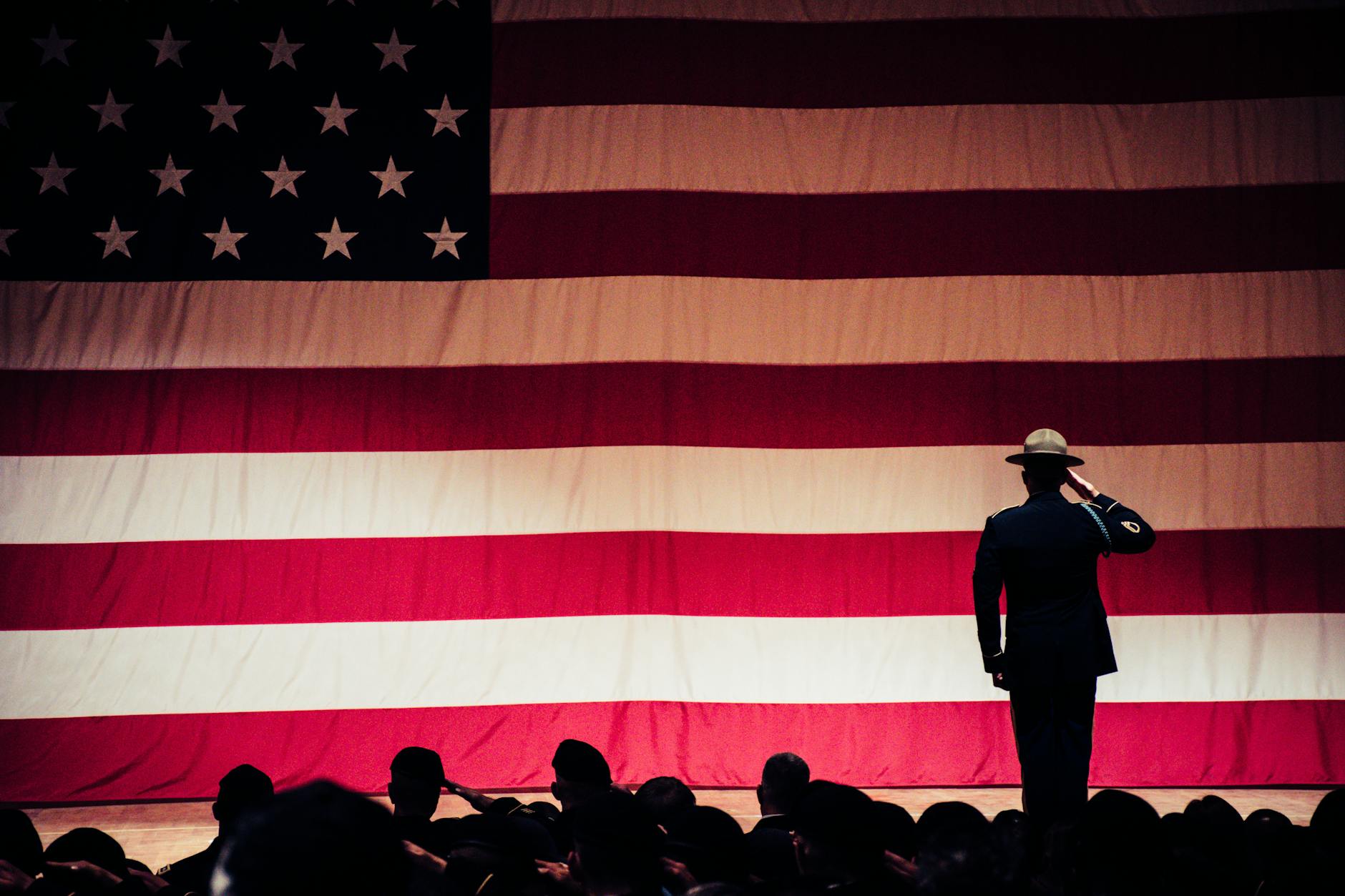日本人が知らないアリゾナ
ナバホ・ネーション
アリゾナ州の5分の1位の敷地は、ナバホ・ネーションと呼ばれるナバホ族の居留区なのです。ナバホ・ネーションは、アリゾナだけでなく、ユタ州の一部と隣のニューメキシコ州の北西部に広がった広大な区域です。
アメリカの先住民の中で、ナバホ族は最大の種族です。連邦政府がここを居留区と定め、独自の種族政府ができています。ネーションとは「国」ですが、外国に行くようなパスポートなどは、ナバホ・ネーションに入る時に必要ありません。
夏場にここをドライブする場合は、一つ、覚えておかないといけないことがあります。
それは、時差です。「エッ同じアリゾナ州の中に時差?」と思うでしょう。それが、あるんですよ。
僕も知らなかったんですが、家族で夏休みを利用してナバホ・ネーションを旅していた時でした。僕らは、一つのビジターセンターに向かっていてました。予め持っていた情報では、午後5時まで開いているというので、4時ころに着けるだろうと計算して、運転して行きました。
そして、到着。僕の腕時計は、4時5分過ぎ。そして、ビジターセンターに行くと、閉まっているじゃあないですか。ナバホの人が勘違いしたのか、と思ったんです。ところが、よく考えてみたら、ナバホ・ネーションは、アリゾナ州内でも、時間が隣のニューメキシコ州に合わせていることを思い出したんです。
アメリカは、広大な国です。そこで、各州がデイタイム・セービングと言って、日が長くなる夏場は、1時間早くなるシステムを取っています。隣のニューメキシコもそうです。
ところが、アリゾナ州だけは、それをしないんです。これが、頭の混乱を起こす原因です。僕は、仕事などで他州の人との電話などで通信をしますが、夏場は、ニューヨークと3時間の時差。冬場は、2時間の時差になります。時々これを間違いて、電話をしたら、向こうはすでにオフィスを閉めていた、なんてことを何回も経験しています。
そこで、夏場のナバホ・ネーションなんですが、ここは、たとえアリゾナ州の中でもニューメキシコ州の時間なので、1時間の時差があります。
ナバホ・ネーションを出入りをする人たちは、その度に時計を直すという作業をする必要があるんです。もっとも最近は、携帯電話が自動的に時間調整をしてくれますけれど。
ここをドライブする時は、ちょっとラジオのスイッチを入れてみて下さい。全く意味のわからない言葉がスピーカから聞こえてきます。これは、ナバホ語です。時々、英語の単語が入っているのに気がつきますが、あとは、何もわかりません。
この言葉が第二次世界大戦で日本軍を困らせた暗号としてアメリカ軍が使ったという事実があります。それは、後ほど触れてみたいと思います。
ウィンドー・ロック
ナバホ・ネーションの首都は、ウィンドー・ロックという町です。この町は、アリゾナの東端にあり、隣のニューメキシコ州との州境に近い場所にあります。ウィンドーとは「窓」でロックは「岩」です。ここのシンボルは、大きな岩に巨大な穴が空いていて、窓のように見え、ナバホの人々にとって聖地です。この場所では、長い間、伝統的な儀式を行われてきました。

ナバホ族は、他の多くの先住民と同様に、白人から受けて来た迫害の悲しい歴史があります。その中でこの居留区は、彼らの独自な文化を保護継承していく場所でもあります。
僕は、多くのナバホの人たちとも友達になりました。ナバホ・ネーションだけでなく、フェニックスなどの都市にもたくさん住んでいます。
ナバホと日本との興味深い縁がありますが、それは、後ほど触れたいと思います。
モニュメント・バリー

ナバホ・ネーション中の何箇所かは、すでに観光地として日本人の間でもよく知られています。例えば、モニュメントバリー。西部劇で有名なジョン・ウェインが主演の映画では、そのロケーションとして使われ、世界中で知られるようになりました。
最近は、ここも観光化がかなり進み、今では、毎日何台も観光バスがひっきりなしに旅行客を連れて来ます。日本からの観光ツアーの一部にも入っていることが多いはずです。
アンテ・ロープ・キャニオン

アンテロープ・キャニオンは、世界中から訪問者が耐えず、その岩と光の美が多くの人を魅了してやまない毎日です。僕が行った時も、ものすごい多くの団体客がきていました。ここでも中国語が飛び交っていました。
ただ、アンテロープ・キャニオンには、アッパーとローワーの二つがあります。二つともいわゆるスロット・キャニオンという岩と岩の間が極端に狭い空間ができている所です。キャニオンとは、「谷」の意味ですが、ここは、谷と言うより、岩のひび割れの中に入って行く感じです。
なぜここが人気があるかと言うと、光です。上から割れ目を通って入ってくる太陽光線が赤い岩の表面に当たり、反射し、実に見事な色彩のある光景を作ってくれるんです。ここは、カメラを持って行き、しっかり写真を撮らないといけませんね。
アッパーは、比較的観光化が進んでいて、駐車場からナバホの人が運転するジープでキャニオンの入り口に行き、そこから、ジープで来た人数分だけグループごとにキャニオンの中に入って行きます。中で、時々、ナバホの人がフルートで音色を流してくれ、何とも言えない雰囲気を作り上げます。また、カメラを抱えていると、ナバホのガイドさんが、シャベルで砂を宙に撒きます。すると、太陽の光線が砂に反射し、誠に神秘的な写真を撮ることができるんです。岩に落ちた砂がサラサラと下に落ちていきます。それにレンズを向けると、まるで絹の布が落ちているように見えます。
さすがガイドさんは良く知っている。
それから一年後にローワーのキャニオンに行きました。ここは、入り口でナバホの人に入場料を払います。ガイドが必要かと聞かれたので、「ノー」と答えると、「それじゃあ、勝手に自分で行ってくれ」と言われました。ここローワーは、アッパーよりも狭い空間を岩肌に体を沿うようにして歩くのです。ですから、一般観光客は少なく、プロの写真家がよく訪れます。
さて、歩いていくと岩の割れ目が見えました。割れ目から下を覗くとハシゴが備え付けられています。このハシゴをつたって下まで降ります。僕は、カメラバッグを背に、そして三脚を手に持って四苦八苦しながら下まで降りました。
さっきあのナバホの人が入り口で「勝手に行け」と言った後、「何かあっても助けに行くのは困難だからな」と言われたのを思い出しました。
そう言えば、ここにくる前にネットで昔ここで死んでしまったカメラマンの話が頭に蘇って来ました。
それは、ヨーロッパからここに来た訪問客に起きた惨事です。雷雨が降り出したのです。すると、この周辺は、一気に洪水になり、鉄砲水がこの狭い谷間に入り込んで来ました。彼らは、行き場がなく、全員溺れ死んでしまったと言うことです。僕はここに来る前によく天気予報を見て、雨が降らないことを確認しましたが、何かあったら困るなあと思いながら、降りて行きました。
さて、最初は良かったんですが、進めば進むほど、空間が狭まっていきます。僕は体が痩せているんですが、この細い僕でも窮屈になるほど、岩と岩の間の距離が縮んできます。三脚を持っていましたが、それさえもセットする場所が見つかりません。とにかく狭い。
ここに水が入って来たら、僕は必ず死ぬだろう、などと思いながら、進ん行きました。
ようやく反対側の出口に出ることができた時は、達成感が心を満たしいました。たくさん写真を取りました。
後で、自分が撮った写真をゆっくり見ましたが、何回見ても飽きることがありません。それほど、素晴らしい自然の芸術作品なのです。

キャニオン・デ・シェー

ナバホ・ネーションの中でも、余り、日本人が知らない自然美の場所もあります。例えば、キャニオン・デ・シェー。ここは、国定公園に指定されています。観光化は進んでいないので、人混みはありません。ここの見所は、何と言っても、「スパイダー・ロック」というものすごい高い塔のような岩です。この岩は2本の柱が隣り合って立っています。地上120メートルの高さです。これは、見れば見るほど、不思議な思いが湧いてきます。僕は、2回訪れました。風が結構強くて、谷に自分が落ちて行くんじゃないかと足がすくむほどでした。このスパイダー・ロックは、谷の底から突っ立っていますが、観光客が見るのは、それより上の崖端ですので、見下ろすようになります。谷の底に行って、ナバホ族の人がジープでツアーをしてくれるようですが、僕は、そこまで降りて行くのはやめました。崖の向こう側には、かつての先住民が残した遺跡が保存されています。望遠レンズで写真を撮りました。


ペインテッド・デザートとペトリファイド・フォレスト
ペインテッド・デザートは、ペトリファイド・フォレスト国立公園に隣接しています。ペインテッド、つまり塗り絵をしたような砂漠ということでしょう。そして、ペトリファイド・フォレストは、化石の森です。

ペインテッド・デザートは、確かにその中の通り、だれかが色を塗ったように、小さな丘の側面に横線が入っています。これは、地層の色ですが、その鮮やかな色彩が、そしてその規模が見事なものなんです。
その中を走る道路は一本道で、時々、車を止めてゆっくり眺めてみると、誰かの塗り絵のように感じます。
ペインテッド・フォレストは、その昔、地球上の大陸が一つに繋がっていて、アリゾナは、赤道近くに位置していた時があったんです。そして、亜熱帯地域で、恐竜が我が物顔で歩いていた頃、この一帯は、森林地帯。その森林が気象の変化で姿を消え去る時、無数にあった木々が地に倒れ、化石化したままアリゾナの地上に残ったんです。

大木が倒れてそのまま化石となって横に寝たような風になっているものもあれば、細かく砕かれて、小さな石のようになっているものもあります。
ここには、標識が立っていて、化石を一つでも国立公園の外に持ち出すと罰金が課せられると書いてあります。持ち出す人も結構いるようですが、公園の保護に協力しましょう。